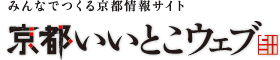だるま寺として親しまれている法輪寺のすぐ近くに、2023年の「和菓子の日(6月16日)」に合わせ、白い暖簾を掲げた和菓子店「兎亀屋(ときや)」があります。

店主は、京都の老舗和菓子店で10年以上にわたり修行を積んだ西澤誘祐(ゆうすけ)さん。同じく和菓子職人である妻とともに始めたこのお店。格子戸を開けると、優しい木の風合いに包まれた品のある空間が広がり、訪れる人を京菓子の雅な世界へ誘います。

大学卒業後に飛び込んだ、未知なる和菓子の世界

京都市出身の西澤さんが和菓子の世界へ進んだのは、和菓子への興味からではありませんでした。もともと粘土を使った写実的な造形に取り組んでいたことから、「ものづくり」ができる製造業を志して就職活動。大学OBとの出会いを機に京都の和菓子屋で和菓子づくりに携わるようになります。当時は「いつか独立しよう」と考えておらず、和菓子の道を歩み続けるかどうか悩んだこともあったそうです。
老舗で培った技と観察力が生む京菓子の美
そんな西澤さんの気持ちの変化は、京菓子の世界を学んでいく中で育まれたといいます。丸みを帯びた形と限られた色数でつくる抽象的な見た目と、菓銘で季節の情緒を表現するのが京菓子だという西澤さん。自身が好きで取り組んできた粘土による写実的なものづくりとは真逆の表現のように思いますが、共通点があったそうです。
「京菓子は飾りに頼らないからこそ、テーマとなる対象物の観察が重要です。粘土造形で必要だった『ものをとらえて観察する力』が和菓子づくりにも活きていると感じました。テーマとなる草花や情景の何を足して何を引くのか。じっくり観察して意匠を練る過程はとても楽しいです。それに『そのお菓子が何を表現しているのか』、お客様に想像して楽しんでいただけるところも和菓子の魅力だと感じます」。

修行先で抱いた和菓子教室の夢が自身の店へ
また、独立前に勤めていた「亀屋良長」での和菓子教室も西澤さんに大きな影響を与えました。体験されたお客さんの喜ぶ姿にやりがいを感じ、独立して和菓子教室を運営していこうと考えたほどです。
当初は店舗を構えるのではなく場所を借りての教室運営を考えていましたが、人との出会いが縁を呼び、現在の物件と巡り合います。もともと製麺所だった建物で、工房・販売・体験教室のスペースを確保できる十分な広さ。「自分のお店を持つとは思っていませんでしたが、せっかく良いご縁に恵まれたのだから、成り行きに任せてみようと思ったんです」と当時を振り返ります。

伝統と遊び心が織りなす京菓子と、楽しみ広がる和菓子教室
「兎亀屋」のメイン商品は、季節の上生菓子と干菓子です。上生菓子は季節に合わせて常時4〜5種類。干菓子は季節限定商品と通年商品を用意されています。

干菓子の菓子型は、食品用の樹脂で西澤さん自身が制作。和菓子だけでなく型までも自作するのは珍しく、同業者から驚かれることも多いそう。独立にあたって、まず用意した型は下記の3シリーズです。
●「うさぎとかめ」:屋号であり、縁起の良い意匠であるウサギと亀。店主がウサギ年で亀が好きという微笑ましいエピソードもあります。

●「ベーカリー」:パン文化が息づく京都にちなみ、クロワッサンやメロンパンの形をした干菓子。パンの味はしませんが、シナモンやキャラメルなど洋の風味をプラス。

●「旬果旬菜」:京野菜や果物をかたどった干菓子。どの角度から見ても楽しめる立体感が魅力。

また、上生菓子や干菓子づくりが体験できる和菓子教室は、曜日限定の事前予約制で開催しています。和菓子の新しい楽しみ方を見つけてほしいという想いで、つくり方や和菓子の魅力をレクチャーする西澤さん。実際「和菓子づくりの苦労や工程がわかったことで、和菓子の見え方が変わった」という声が体験者から届いています。

広がる活躍の場、最新情報はSNSをチェック
22歳で和菓子の世界に飛び込み、和菓子づくり、菓子型制作、和菓子教室と日々奮闘している西澤さん。
美術館とのコラボレーションやお寺で提供する和菓子制作など、活躍の幅も広がっています。「和菓子づくりが本当に楽しくなってきたのは、ここ最近のことかもしれません」とほほ笑む様子からは充実感もにじみでていました。

販売中の和菓子の意匠や最新情報は、ぜひお店のInstagramでチェックしてみてください。そして、次の京都訪問では、「兎亀屋」に足を運び、京菓子の奥深い楽しみを、じかに体感してみてはいかがでしょうか。確実に手に入れたい和菓子は予約がおすすめです。
■兎亀屋
https://www.instagram.com/tokiya.wagashi/
見ているだけで不思議と心地よい、干菓子の製造風景!「兎亀屋」のショート動画はこちら