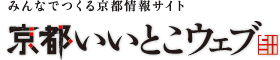仏壇で手を合わせる時、「リーン」という穏やかな音色を響かせる「おりん」。その音に、思わず背筋がのびたり、心が安らいだりした経験はありませんか?

この「おりん」をはじめ、お祭りやお寺・神社で使う鳴物神仏具(なりものしんぶつぐ)を専門に製造してきた工房が、京都府宇治市にあります。それが「南條工房」です。
理想の音色を生む二つのこだわり
「南條工房」が最も大切にしていること。それは「音」です。波打つことなく一定の調子で長くのび、境目がどこにあるのかわからないほど静かに消えゆく余韻を目指しています。
まずはこちらの動画でその音色を聞いてみましょう。
引き込まれるような澄んだ音色に、気持ちも静まりませんか?「南條工房」では、この理想の音を追求するために、昔からこだわってきた2つのポイントがあります。
- 独自配合の「佐波理(さはり)」

一般的に「おりん」は、銅と亜鉛を混ぜた真鍮(しんちゅう)製が多い中、「南條工房」では銅と錫(すず)を混ぜた佐波理(さはり)という合金を使います。佐波理は、奈良の正倉院に佐波理製の宝物が残るほど伝統的な材料です。
通常、佐波理の錫の含有率は15~20%といわれますが、「南條工房」は錫の量を増やした独自の配合でつくります。これは「南條工房」の先々代にあたる5代目が研究を重ねて生み出した配合率。錫を多くして硬さをアップさせることが、理想の音色に不可欠だそうです。
- 手間をかけても「焼型鋳造法(やきがたちゅうぞうほう)」

佐波理を使ってどう「おりん」をつくるのか。それは「薪窯で焼いた型に、佐波理を流し込む」方法です。弥生時代にも使われていたとされる原始的な製法で、手間も時間もかかる非効率な方法なのだとか。それでも、佐波理を使って最良の音を生み出すには、最適な工法だそうです。
工房見学ツアーで知る、音づくりの現場
「南條工房」では、製造現場をじかに見学できるツアーを実施しています。

ツアーは、工房併設の「LinNe STUDIO(リンネスタジオ)」で、「音」への想いを聞くことから始まります。驚いたのは、失敗作と合格した「おりん」の聞き比べ。素人でもその音の差は歴然で、工房が生み出す音の魅力に引き込まれます。

そのあとは、トタン屋根の平屋がいくつも並ぶ工房へ移動。タイムスリップしたような歴史を感じる空間で、7代目をはじめとした5~6名の職人が作業にあたっています。
南條工房の「おりん」づくりの主な工程
- 型づくりと循環

おりんづくりは型づくりから始まります。
材料は「土」「粘土」「お米のもみがら」「水」。「お米のもみがら」は近所の農家さんから分けてもらい、「水」は雨水をためて使います。つくった型は一度しか使えませんが、使用後は粉砕してふるいにかけ再利用するのが基本。こうした循環型のものづくりを昔から続けています。
- 暑さ厳しい「鋳造(ちゅうぞう)」の日

「乾燥した型を薪窯で焼く」「炉で錫と銅を溶かして佐波理をつくる」「焼きあがった型を地面に並べ、佐波理を流し込む」。この一連の作業を同日に行います。1000度をこえる炉と、500度以上の窯が同時に稼働する現場は、まさに灼熱。
それでも、型の温度、錫と銅の溶け具合、佐波理の流し込みや型から外すタイミング…こうしたことがすべて音の質に関わるため気が抜けません。
過酷な作業の後は、オロナミンCが職人さんたちのマストアイテム。暑い夏場はアイスクリームも欠かせなかったそうです。
※鋳造は作業日が限られているため、通常の工房見学ツアーとは別枠でご案内があります。くわしくはHPをご参照ください。
- 意外と力仕事の削りの作業
型から外した「おりん」は、表面を削って整える加工作業に入ります。

音色に大きく関わる工程なので、現在は7代目だけが行える作業だそうです。

- 厳しい検品
できあがった「おりん」は実際に鳴らして音色をチェック。7代目の耳で厳しくジャッジし、合格品と不合格品に選別されます。不合格になった「おりん」は、削りカスと同じように材料として再利用。無駄にはなりません。
「おりん」の音色を現代の暮らしに
「南條工房」は、長くものづくりに徹してきましたが、自分たちが大切にしてきた音を、より広く伝えていく必要性を感じ「LinNe(リンネ)」というオリジナルブランドを2019年に立ち上げました。
現代の暮らしに溶け込むアイテムを展開し、「LinNe STUDIO」では実際に手に取って、美しい音色を聞き比べることができます。



その結果、「おりん」の使い方は工房の想像をこえて広がっていきました。
坐禅やヨガ、楽器、登山での熊除け鈴、着物の根付として。また、気持ちを切り替えたい時や一日のはじまり・おわりに音色を取り入れ、心身の健やかな日々に役立てている人も増えています。

「人生において、おりんを買う機会は何度もあることではないと思います。だからこそ、まずは私たちが大切にしている音の良さを知ってほしい。そしていつか「おりん」が必要になった時、自分にとって心地の良い音を探しにきてほしいです」と7代目の妻でもある南條由希子さんは語ります。

次の京都旅行では、「南條工房」が守り継ぐ伝統に触れ、心地よい音を探す旅に出かけませんか。
日々の暮らしに豊かさをもたらす自分好みの音に出会えるはずです。
■南條工房
https://www.instagram.com/linne_orin/
■ファクトリーツアーのショート動画