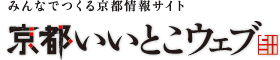行事– tag –
-

京都三大祭 時代祭
毎年10月22日に京都で開催される時代祭。華やかな歴史装束を身につけた大勢の人々が京都のまちを練り歩くこの祭りは、葵祭、祇園祭と並んで京都三大祭のひとつに数えら... -

京都東山「高台寺」でアンドロイド観音、3/8より一般公開
豊臣秀吉の正室・北政所が秀吉の菩提を弔うために建立した「高台寺」。多くの人に仏教に興味を持ってほしいという想いで、世界初のアンドロイド観音「マインダー」を大... -

「わたしの盆踊りエピソード写真展」、8/6まで開催
大谷大学の社会学科の学生たちが京都市左京区で行った、 フィールドワークの結果をまとめた写真展が8/6まで開催中です。 テーマは「盆踊り」。 左京区に住む70~80代シ... -

1/7は七草粥
1月7日にいただく春の七草粥。 せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ。 七草粥は中国のほうに起源があり、平安時代には日本に伝わったとい... -

9月9日は重陽の節句
人日(1月7日)、上巳(3月3日)、端午(5月5日)、七夕(7月7日)の節句に続き、五節句の最後を飾る「重陽の節句」。別名「菊の節句」と呼ばれるように、延命長寿の花... -

8月22日~23日は六地蔵巡り
毎年8月22日・23日に行われる「六地蔵巡り」。これは、都の入口(旧街道)にあるお地蔵さん合計6か所を巡拝し、家内安全・無病息災を祈るというもの。すでに800年以上の歴... -

2016年7月の主な行事ピックアップ
7月の京都は祇園祭だけじゃないんです。 参加して楽しい、見て楽しい2016年7月の京都行事ピックアップ! 賀茂御戸代能【薪能】@上賀茂神社 2016年7月1日18時~ 境内の... -

13日は虚空蔵菩薩の御縁日です
丑と寅年生まれの守り本尊で、智恵と福徳を授けてくれる「虚空蔵菩薩」。 13歳(数え年)の男女が成人になった証として虚空蔵菩薩に参拝する 「十三まいり」で知られて... -

冬の風物詩「大根だき」まとめ2015~2016
京都の冬の風物詩にはいろいろありますが「大根だき」もそのひとつ。 京都でも様々なお寺で大根だきが行われます。 主なところをピックアップしました。冬のお出かけの... -

平安神宮で開催、団扇の老舗小丸屋の琳派展
2015年11月27日(金)~29日(日)の3日間、岡崎の平安神宮にて 「平安神宮奉納 小丸屋琳派展 神楽の言ノ葉2015」が開催されます! 小丸屋とは、岡崎にある寛永元年(1...